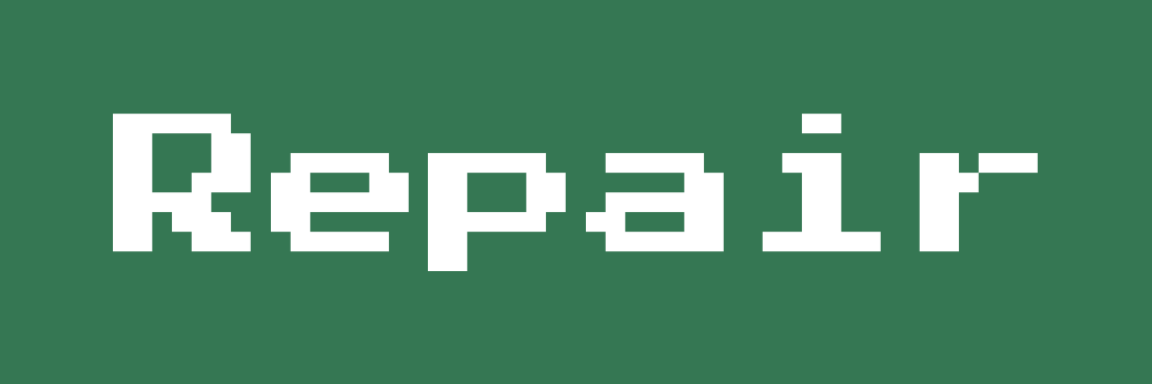オールデン好きはコーヒーにもこだわる
こんにちは、うりちきです。
2025年がスタートしましたね。21世紀が始まって四半世紀、節目の年に新しいチャレンジはいかがでしょうか。
そこで今回から趣向を広げて、「革靴好きがハマるもの」についてご紹介していこうと思います。
さて、早速ですがオールデンファンの方の多くは、「作り手のこだわりを重視する」「長く付き合えるものを大切にする」といった価値観をお持ちではないでしょうか。
そんなこだわり派にこそぜひ知って欲しいのが、コーヒーの世界です。特に「スペシャルティコーヒー」は奥深く、知れば知るほど深みにハマりますよ。
「聞いたことはあるけど詳しくは知らない」「少し気になるけど難しそう」と思っている方に向けて、今回はスペシャルティコーヒーの魅力と、最近のコーヒー事情についてご紹介します。
1. スペシャルティコーヒーとは?
普通のコーヒーとの違い
まずは「スペシャルティコーヒー」と普通のコーヒーの何が違うのか、簡単にご紹介してみましょう。
スーパーやコンビニで手軽に買えるコーヒー豆の多くは、大量生産するために、複数の豆をブレンドして安定した味になるよう調整された「コモディティコーヒー」と呼ばれるものです。
一方、「スペシャルティコーヒー」は、産地ごとの個性を最大限に生かした、品質重視のコーヒーです。
これは、単に高級であるという意味ではなく、香りや味など複数の項目について、指定された基準を満たした豆だけが名乗ることができます。
例えば、ワインがブドウの産地や品種によって味が変わるように、コーヒーも「どこで・誰が・どのように育てたか」によって香りや風味が大きく異なります。
つまり、スペシャルティコーヒーとは、高い品質だけでなく、「作り手のこだわり」が詰まった一杯ともいえる訳ですね。
スペシャルティコーヒーの基準
では、具体的にどのような基準を満たせば「スペシャルティコーヒー」と呼ばれるのでしょうか。
世界には、「SCA(スペシャルティコーヒー協会)」という組織があり、そこで定められた評価基準をクリアした豆だけが、スペシャルティコーヒーとして認められます。
この評価では、「香り」「酸味」「甘み」「後味」「バランス」などの項目が細かく採点され、合格には100点満点中で80点以上のスコアを獲得する必要があります。
また、スペシャルティコーヒーのもう一つの大きな特徴が、「トレーサビリティ(追跡可能性)」です。
一般的なコーヒーは、複数の豆を混ぜて出荷するため、どこの農園で作られたのか分からないことがほとんどですが、スペシャルティコーヒーは生産地や農園、生産者まで明確に特定できるのが非常に面白いポイントです。
例えば、エチオピア産はフルーティーな酸味がある、グアテマラ産はボディ感のあるコーヒーでエスプレッソとしても楽しめる、といったように、産地ごとに全く異なる味わいがあるのが、スペシャルティコーヒーの醍醐味です。

A Shine And GeekのキッチンにはSCAが作成したフレーバーホイールが飾られている
なぜスペシャルティコーヒーは美味しいのか
明確な基準を持って美味しさが担保されたスペシャルティコーヒーですが、これらが美味しくなる理由は、全ての段階で一貫した体制、工程を経ること、品質管理が徹底していることにあります。
例えば、コーヒーの生豆がいわゆる「コーヒー豆」となるまでには、大きく分けて「収穫」「精製」「焙煎」の3つの工程があります。
まず「収穫」の段階では、機械ではなく手摘みで行われることが多く、目視で完熟した豆だけを収穫します。
コモディティコーヒーでは機械で収穫するため、熟していない豆や欠点豆も混ざりやすくなるのですが、スペシャルティコーヒーの場合は収穫時点でそれらの豆がほとんど弾かれます。
次に、生豆の収穫後は、果実の中からコーヒーに必要な種子だけを取り出す「精製」というプロセスがあります。これにはいくつかの種類があり、それによってコーヒーの味の特色が大きく変わります。
代表的なものを挙げると、下記の3つとなります。
- ナチュラル:最も古くからある伝統的な精製方法。水を使わず天日干しにする。フルーティで甘みが強いコーヒーになりやすい。
- ウォッシュド:大きな水槽の中で生豆を発酵させ、果肉部分を取り除く。苦味や雑味のないクリーンな酸味が得られやすい。
- パルプドナチュラル:ナチュラルとウォッシュドの折衷案で、特殊な機械を用いてより少ない水で種子を取り出す。ほどよい果実みと甘さがバランスよく楽しめる。
そして最後に、コーヒーの話題でよく耳にする「焙煎(ロースト)」の違いです。
精製されたコーヒー豆は煎られることで、よく見る焦茶の豆になるのですが、この加熱具合によって酸味や風味のバランスが決まります。
昔ながらの喫茶店で出てくるコーヒーは、香ばしさを重視した「深煎り」のものが多いのですが、スペシャルティコーヒーは豆の個性を活かすため、「浅煎り」から「中煎り」が主流です。酸味やフルーティな風味が際立つので、一般的な「苦いコーヒー」のイメージとは随分と違った印象となりますよ。
まとめると、スペシャルティコーヒーは「厳選された豆 × 適切な精製 × 最適な焙煎」という、徹底的なこだわりによって生まれます。

焙煎所(ロースター・ロースタリー)を見学するのも楽しい
2. 最近のコーヒー事情
「サードウェーブコーヒー」とは?
さて、スペシャルティコーヒーについて概要を紹介したところで、続いて昨今のコーヒー事情について触れておきましょう。
ここ数年、「サードウェーブコーヒー」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。
これは世界のコーヒー文化の流れを、3つの時代(ウェーブ)に分けて捉えたものです。
まず、「ファーストウェーブ(第1の波)」は、それまで上流階級の嗜みだったコーヒーが、一般家庭に普及した時代(20世紀前半)を指します。
インスタントコーヒーや缶コーヒーが誕生し、大量生産・低価格化が進むことで、「コーヒーを楽しむ」ということが誰にとっても身近なものになりました。
第二次世界大戦の終結後、コーヒーの需要は一層高まり、日常的に飲むコーヒーの味や品質を重視する流れが強くなってきました。
それが表面化したのが1970年代頃から広まった「セカンドウェーブ(第2の波)」で、スターバックスなどのカフェチェーン店が世界的に広がった時代です。
ただの飲料品としてのコーヒーだけでなく、エスプレッソを使ったカフェラテやカプチーノが一般的になり、いわゆる「カフェ文化」が定着しました。

エスプレッソとは粉に高い圧力をかけて摘出するスタイルです
そして、今まさに主流となっているのが「サードウェーブ(第3の波)」で、現在は「第三次コーヒーブーム」ともいえる時代ということですね。
これは、「コーヒーを嗜好品として楽しむ」という考え方で、より好みに合ったコーヒーを楽しむために、豆の産地や精製方法、焙煎具合までこだわり、作り手の個性を重視する文化が広まっています。
もちろん人によって嗜好は異なるのですが、サードウェーブらしい特徴としては、
- 豆の個性を活かすために「浅煎り」が主流
- シングルオリジン(単一産地の豆)が人気
- 一杯ずつ丁寧に淹れるハンドドリップが好まれる
といったポイントが挙げられます。
つまり、サードウェーブはクラフトマンシップを重視する流れ、ともいえそうです。
靴で例えるならば、大量生産のスニーカーではなく、職人が作るグッドイヤーウェルテッド製法の革靴を楽しむ感覚に近いですね。

A Shine And Geekが愛用するグラインダー。同じ豆であっても、粒度、温度、摘出時間などによって味が変わる
フェアトレードとサステナビリティ
また、最近のコーヒー業界では、「フェアトレード」や「サステナビリティ」といったキーワードが重要視されます。
スペシャルティコーヒーの多くは、単に「美味しい」だけでなく、環境や生産者に配慮した倫理的なコーヒーである、ということも非常に重視されます。
例えば、
「適正な価格で取引を行い、生産者の生活向上を支援すること(=フェアトレード)」や、
「化学肥料や農薬を使わず、自然環境に優しい栽培方法であること(=オーガニックコーヒー)」、
「豆を自然の木陰で育てることで、生態系を守りながら栽培すること(=シェードグロウン)」といったものです。
こうした取り組みが広がることで、コーヒーは単なる嗜好品としてだけではなく、「持続可能な農業」や「地域貢献」の一環としても注目されるようになっています。
この流れは、革靴の世界でも似ていますね。
例えば、近年では「エシカルレザー」や、「サステナブルなものづくり」を掲げるブランドが増えています。
「良いものを大切に使い続ける」という価値観も、コーヒーと革靴の世界で共通するポイントかもしれません。
スペシャルティコーヒーを楽しむ
日本でもスペシャルティコーヒーの人気は年々高まっており、専門店やロースター(焙煎所)が続々と増えています。
例えば、米国発のサードウェーブ代表格である「Blue Bottle Coffee(ブルーボトルコーヒー)」や、京都発の人気店「% Arabica(アラビカ)」、東京中目黒のロースター「ONIBUS COFFEE(オニバスコーヒー)」などですね。
このような店では、バリスタがハンドドリップで一杯ずつ丁寧に淹れたコーヒーを頂くことができます。
豆の種類も豊富で、「エチオピアのフローラルな酸味」や「グアテマラのチョコレートのような甘み」など、産地ごとの違いを楽しむこともできますよ。
また、最近では「家で楽しむコーヒー」にも注目が集まっています。
ミルで豆を挽いてハンドドリップで朝のコーヒータイムを楽しんだり、アウトドアの場面でも「エアロプレス」といった道具を使えば屋外で手淹れのコーヒーが楽しめます。
インスタントコーヒーであれば1分足らずですが、あえて自分で豆を挽き、お気に入りの器具でゆっくりとコーヒーを淹れる。そんな時間が、日常を豊かにしてくれそうです。

エアロプレスという道具を用い加圧して摘出する比較的新しいスタイル
3. こだわり派におすすめのスペシャルティコーヒー
スペシャルティコーヒーの魅力が分かってきたところで、「実際にどんなコーヒーを選べばいいの?」と思う方もいるかもしれません。
そこで最後に、初心者でも試しやすい、おすすめのスペシャルティコーヒーの産地と特徴を、3つご紹介します。

※写真はイルガチェフェのコーヒー協同組合のサイトから
エチオピア(イルガチェフェ)
アフリカのエチオピアはコーヒー発祥の地ともいわれ、現在でも世界で5番目に生産量の多い国です。
特にイルガチェフェ地方のコーヒーは、フルーティで華やかな香りが特徴です。
- 味わい:紅茶のような軽やかさ、柑橘系の爽やかな酸味
- おすすめの焙煎:浅煎り
「コーヒーは苦いもの」というイメージのある方は、まずはこのフルーティな酸味が新鮮に感じるでしょう。
スペシャルティコーヒーの世界に足を踏み入れる第一歩としてもおすすめです。
コロンビア(ウィラ)
南米のコロンビアは安定した品質のコーヒーが多く、日本でも特に人気の高い産地です。
クセが少ない豆が多いのですが、特にウィラ地方のコーヒーは、酸味と甘みのバランスがよく、非常に飲みやすいことが特徴です。
- 味わい:ナッツのようなコク、チョコレートのような甘み
- おすすめの焙煎:中煎り
毎日飲んでも飽きのこない、安定感のある味わいは、「酸味やクセが強すぎるのは苦手だけど、スペシャルティコーヒーを試してみたい」という方にもぴったりです。
グアテマラ(アンティグア)
中米グアテマラのコーヒーは、しっかりとしたコクがありつつ、程よい甘みが楽しめるのが魅力です。
特にアンティグア地方のコーヒーは、火山に囲まれた土壌で育つため、独特の深みがあります。
- 味わい:チョコレートのような上品なコク、ほのかな柑橘系の酸味
- おすすめの焙煎:中深煎り(シティロースト)
コクのある味わいが好きな方や、ミルクを入れて楽しみたい方にもおすすめです。
ボディ感のあるコーヒーなので、エスプレッソで楽しむのも良いですね。
まとめ
今回は、「スペシャルティコーヒー」の概要や魅力と、昨今のコーヒー事情についてご紹介しました。
革靴やオールデンのように、「こだわりを持って選ぶからこそ楽しめる世界」が、コーヒーの分野にも広がっています。
スペシャルティコーヒーの奥深さを知るためには、まずは実際に一杯飲んでみるのが一番です。
ぜひお近くの専門店に足を運んで、バリスタの淹れる一杯を頂いてみてください。
自宅で楽しむ場合は、シングルオリジンの豆を専門店で購入し、まずはハンドドリップで淹れてみるのがおすすめです。
お店で豆を挽いてもらうこともできるので、ペーパーフィルターとドリッパーさえ用意すれば、意外と手軽に始めることができますよ。
淹れたての香りを楽しみながら、ゆっくりとコーヒーを味わう時間は、革靴の手入れをするひとときにも通じるものがあります。
オールデンとこだわりの服を纏って出かける、その前にお気に入りのコーヒーを楽しむ、そんな豊かな時間に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【ご支援のお願い】
「オールデンのコードバンが大好き by A Shine And Geek」にご訪問いただき、ありがとうございます。私たちのサイトは、快適なユーザー体験を提供するため、広告収入に頼らず運営しています。広告なしでサイトを維持し続けるために、皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。もしサイト内の情報に価値を感じていただけましたら、質の高い記事をこれからも提供していくために、以下のイーサリアムアドレスへの寄付をご検討いただければ幸いです。ご支援いただいた方には、サポーターの証として「A Shine And Geek」のエンブレムNFTをお贈りいたします。また特別ページにてSNSアカウント等のお名前紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【 ashineandgeek.eth 】