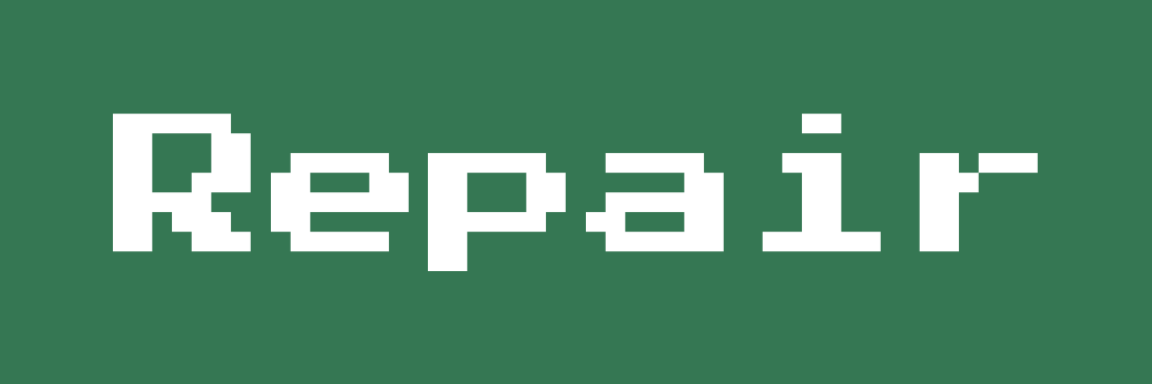こんにちは、うりちきです。
夏も本番、朝の光が一層まぶしくなってきましたね。
日の出も早いこの季節、少しだけ早起きして、自分だけの時間を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。
仕事前の爽やかな朝に、革靴を磨いたり、ゆっくりコーヒーを淹れたり。どちらも、一日の始まりにふさわしい、丁寧で穏やかな時間ですね。
さて、本ブログでは以前に、スペシャルティコーヒーの魅力や、豆の産地による味の違いについてご紹介しました。
「自分でも淹れてみたくなった」という方に向けて、今回は『家でコーヒーを淹れるための道具』について取り上げてみます。
オールデンと同じく、『自分に合う一品』を見つける楽しさをぜひ味わってみてください。
▶︎関連過去記事はこちらからどうぞ
最初の一杯を楽しむために:初心者が揃えたいハンドドリップの『基本ギア』
「自分でコーヒーを淹れてみたいけど、道具が多くて難しそう」
そのようなことを感じる方も多いかもしれません。ですが、ハンドドリップに必要な道具は、実は意外に少なくてシンプルです。
ここでは、これからハンドドリップを始めたい方に向けて、最初に揃えたい基本の5つの道具をご紹介します。
コーヒーギアには、絶対の正解がありません。
最初は高級なギアや難しいテクニックにこだわらず、まずは「お湯を注げば香りが立ちのぼる」その瞬間を楽しんでみてください。

まずはドリッパーを集めたくなりませんか?
1. ドリッパー
ハンドドリップを想像した時、最初に思いつくのがこの「ドリッパー」でしょうか。
ドリッパーは、紙のフィルターをセットして、挽いた豆を入れてお湯を注ぐための器具です。
コーヒーの味に淹れ手の個性を反映させる『最初の一手』ともいえるギアでしょう。
主な形状は「台形タイプ」と「円錐タイプ」の2種類に分かれます。
台形型はお湯がゆっくりと流れ、味が安定しやすいため、初心者にとって扱いやすいといわれます。
一方で円錐型は、お湯の注ぎ方で味の印象が変わりやすく、慣れてくると自分なりのコントロールを楽しめるのが魅力です。
また、材質もプラスチックからガラス、陶器、金属まで様々で、それぞれ保温性や質感が異なります。
最初の一つとしては、軽くて扱いやすいプラスチック製などが気軽でおすすめです。
ドリッパーの形や素材によって、コーヒーの味わいや香りの出方は違ってきます。
ある程度慣れてきたら、異なるタイプのドリッパーを追加して、それぞれの違いを実感してみるのも楽しいですよ。

記事にはありませんが匂いを除去するためにお湯を流しますよね?うりちきさん
2. ペーパーフィルター
ドリッパーを入手したら、一緒に使う「フィルター」も用意しましょう。
これがないと、コーヒーの粉がカップに落ちてしまいます。
フィルターの形状は、ドリッパーとセットで考える必要があります。
台形用と円錐用で形が異なるため、購入時には対応する形をよくチェックしましょう。
素材や厚みによっても、抽出のスピードや味わいに差が出るのですが、最初のうちはあまり難しく考えず、素直に定番のものを使うのがおすすめです。
ただ、一見消耗品のようなフィルターですが、コーヒーの味を支える縁の下の力持ちかもしれません。
こだわり始めると「漂白のあり・なし」「クレープ加工のあり・なし」などにも興味が湧いてくるのが、コーヒーギアの面白いところです。

左のカッター式は粒度が揃わないのでお勧めしません。手動のミルで豆の抵抗を感じながら丁寧に挽いてみましょう。
3. コーヒーミル
あらかじめ挽いてある豆を購入する場合は、最低限「ドリッパー」と「フィルター」があればコーヒーを淹れることができます。
しかし、そのままのコーヒー豆を使用するなら、さらに「コーヒーミル」が必要となります。
挽きたての豆で淹れたコーヒーは、香りが全く違います。
焙煎された豆の香ばしさが、挽いた瞬間に最も香りが立つ。その瞬間を、ハンドドリップの最大の魅力という愛好家も多いです。
さて、ミルには大きく分けて「手動タイプ」と「電動タイプ」がありますが、最初の一台としては、手挽きタイプがおすすめです。
少し時間はかかりますが、段々と粒が細かくなっていく感触を味わいながら、静かな朝のひとときを楽しむにはぴったりのギアではないでしょうか。

1gの誤差も許さないオタクの私たちは細口ケトルを選ぶ
4. ケトル
ここからは、ハンドドリップに必須ではないですが、あるとより便利なギアの紹介です。
豆にお湯を注ぐには、ご家庭にある普通のやかんやポットでも良いのですが、ハンドドリップに慣れてくるとまず欲しくなるのが「細口のドリップケトル」です。
いかにも『ハンドドリップらしい』すらりと伸びた細い注ぎ口は、お湯を少しずつ、狙った場所に正確に注ぐための形です。
これがあると、注ぎのコントロールがしやすくなり、仕上がりにも安定感が出てきます。
電気式でも直火用でもOKですが、ここは「自分にとって使いやすい」ことが何より大切でしょう。
デザインの好みも含めて選ぶのも楽しいですね。
5. スケール、温度計
最後に、少しだけ実用的なアイテムのお話しです。
コーヒーの味は「豆の量」「お湯の量」「温度」「抽出時間」で大きく変わります。
そのため、それらを見える化してくれる道具があると、味が格段に安定してきます。
まずは「スケール(はかり)」です。
豆やお湯の量を正確に量れるだけでなく、最近のドリップ用スケールには「タイマー機能」がついているものも多く、お湯を注ぐスピードや全体の抽出時間をきちんと管理できます。
そして「温度計」もあると便利ですね。
コーヒーの抽出に理想的なお湯の温度は、だいたい92~96度の間といわれています。
温度計があると、その範囲を狙いやすくなりますし、温度による味の違いを試してみるのも面白いです。
はじめから完璧に揃える必要はなく、「味を一定にしたい」「再現性を高めたい」と思い始めたタイミングで手に取ってみるのがいいですね。
道具を揃えたら:ハンドドリップの基本的なやり方紹介
必要な道具が揃ったら、いよいよコーヒーを淹れてみましょう。
初めのうちはあまり難しく考え過ぎず、「香りが立てばまずはOK」くらいの気持ちで始めるのが、長く楽しむコツです。
ここでは、基本となるハンドドリップの流れを5つのステップに分けてご紹介します。
最初のうちは少しバタつくかもしれませんが、慣れてくると自然と手が動くようになりますよ。
1. 豆を挽く(中細挽きが基本)
まずは、コーヒーミルを用意した方は、飲む直前に豆を挽きましょう。
ペーパーフィルターを使う場合、粒の大きさは「中細挽き」が基本です。
好みもありますが、挽き目が細かくなるほど味や苦味が強く出やすい、とイメージしてください。
初めのうちは毎回挽き目を少し変えてみて、「自分の好きな味」を探っていくのも楽しいですね。
2. 湯を沸かす(92~96度が目安)
お湯の温度は、コーヒーの味を左右する大きな要素です。
理想は92~96度、深煎りなら少し低め(90度前後)で淹れる方も多いです。
熱すぎると苦味が強くなり、ぬるすぎると酸味や香りがぼやけてしまいます。
温度計がない場合は、日本茶を淹れる時のように、一度カップを経由させて冷ますことでも温度が安定しますよ。
3. ペーパーをセット、挽いた豆を入れる
次に、ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、挽いたコーヒー豆を入れます。
豆の分量は、カップ一杯(約200ml)に対して10~12gが目安です。
お湯を注いだ時に抽出が不均一にならないよう、ドリッパーを軽くゆすって粉の表面を平らにしておくのがポイントです。
ちょっとした工夫ですが、味の安定感がぐっと増しますよ。
4. 「蒸らし」→「2~3回に分けて注ぐ」
いよいよ抽出のメイン工程です。
まずは少量のお湯で豆を軽く湿らせ、20~30秒ほど「蒸らし」の時間をとります。
※A Shine And Geekからひとこと
私はこの待ち時間を使って必ず腕立て伏せをします。カフェインを摂取するたびにマッチョになっていくなんて、もしかして意識高い?
この間に豆の内部に残るガスが抜けて、コーヒーの味がしっかり抽出されやすくなります。
その後、2~3回に分けて、ゆっくりお湯を注いでいきます。
コツは、フィルターの紙に直接お湯を当てないことと、低い位置から静かに注ぐことです。
焦らず丁寧に、それだけで雑味の少ない仕上がりになりますよ。
5. 時間と湯量を計る
ここまでが基本的なハンドドリップの淹れ方ですが、スケールとタイマーがあれば毎回安定した味を出せるようになります。
蒸らしを含めた全体の抽出時間は、2分半から3分くらいが目安です。
また、それぞれの工程でどれぐらいずつお湯を注ぐのか、どのぐらいのスピードで注ぐのか、全てが味に関わる『変数』です。
同じ豆でも、淹れ方で随分と味が違ってきます。
「この組み合わせが一番好きかも」と、自分好みのバランスを見つけるのもまた楽しい時間ですね。

カップ一つとってもファイヤーキングのようなアメリカンスタイル、ヨーロピアンスタイル、陶器や磁器、木製など様々あり、キリがありません。
知識が深まるとより面白い:『本格ギア』へのこだわり
さて、コーヒーを淹れることに慣れてくると、ふと「もっと道具にこだわってみたい」と感じる瞬間がきっとやってきます。
オールデン好きの方が、ラストの違いやウェルト形状にまでこだわるように、コーヒーギアの世界もまた、知識が深まるほど面白くなっていきます。
ここでは、そんなこだわり派の入り口として、使い心地だけでなく素材や表情にも惹かれる「本格ギア」の一端をご紹介します。
1. 金属製ドリッパー
一般的なプラスチックや陶器のドリッパーに比べて、金属製のドリッパーはお湯の温度が安定しやすいという利点があります。
特に銅は熱伝導性が高く、お湯の温度をしっかりキープできるため、風味がブレにくくなります。
また、金属製のドリッパーは使い込むほど表情が変わり、長く愛用できるというのも大きな魅力ですね。
革靴を履き込んでエイジングを楽しむように、コーヒーギアにもまた『育てる道具』としての面白さがあります。
2. ホーロー・銅・電気式のケトル
一見「お湯を沸かすだけ」のケトルも、実は奥が深い道具です。
たとえば、ホーロー製のケトルは保温性が高く、お湯が冷めにくいため、ゆっくりと落ち着いてドリップできます。
逆に、銅製のケトルはお湯が沸くのが早く、使うほどに味の出る見た目も魅力です。
最近では、温度設定ができる電気式のドリップケトルも人気です。
湯温をより細かく管理できるので、豆の種類や気分に応じた「温度で遊ぶ」楽しみが広がります。
3. 布フィルター
ペーパーフィルターとは違った魅力を持つのが、ネルドリップに使われる布フィルターです。
やや目が粗く、豆の油分(コーヒーオイル)が多く抽出されるため、コクがあって丸みのある味わいに仕上がります。
都度洗って使う必要はありますが、その手間がかえって道具への愛着を育ててくれるかもしれません。
『使い捨てではない』ことで、オールデンのように「長く付き合う」道具としての深みを感じさせてくれますね。
まとめ
今回は、ハンドドリップでコーヒーを楽しむための道具について、初心者向けの基本ギアから、こだわり派に向けた本格ギアまでご紹介しました。
コーヒーギアの魅力ですが、「正解がない」ことにもあるのではないでしょうか。
機能性はもちろん、見た目に惹かれてもいいし、手に馴染む感触で選んでもいい。
自分にとっての最適を少しずつ見つけていく、そんなプロセス自体がコーヒーの楽しさの一つ、かもしれませんね。
爽やかな朝の時間や休日の午後。自分だけの時間を彩る道具として、コーヒーギアの世界を少しずつ広げてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂きありがとうございました。
【ご支援のお願い】
「オールデンのコードバンが大好き by A Shine And Geek」にご訪問いただき、ありがとうございます。私たちのサイトは、快適なユーザー体験を提供するため、広告収入に頼らず運営しています。広告なしでサイトを維持し続けるために、皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。もしサイト内の情報に価値を感じていただけましたら、質の高い記事をこれからも提供していくために、以下のイーサリアムアドレスへの寄付をご検討いただければ幸いです。ご支援いただいた方には、サポーターの証として「A Shine And Geek」のエンブレムNFTをお贈りいたします。また特別ページにてSNSアカウント等のお名前紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【 ashineandgeek.eth 】