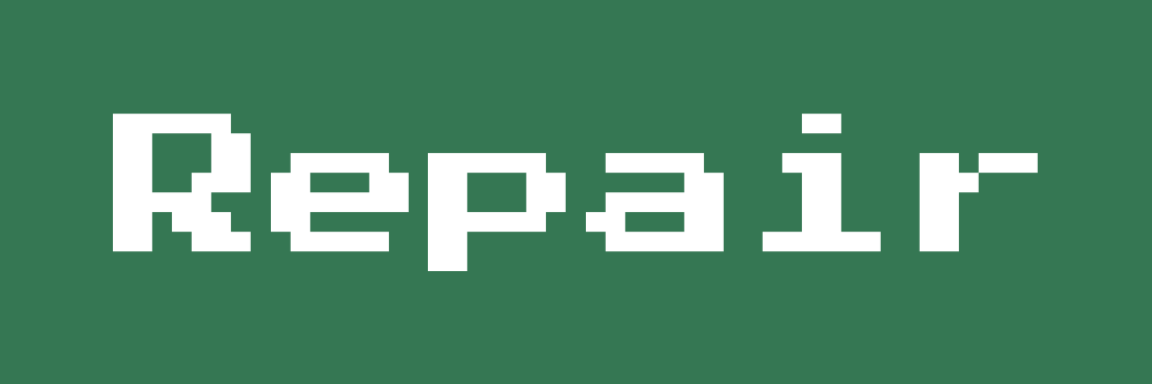こんにちは、うりちきです。
今回は、先日ご紹介した「SHOESHINE GRAND PRIX 2025」の会場で目にした、ちょっと気になる発信について少しだけ取り上げてみたいと思います。
それが、タイトルにもある「革って、サステナブル」というメッセージです。
大会会場では、日本の革産業を支援する一般社団法人JLIA(日本皮革産業連合会)による広報が配布され、「革とサステナビリティ」について考える発信が行われていました。

※画像は一般社団法人JLIA(日本皮革産業連合会)のサイトから
革製品が「持続可能」である理由
まず「サステナブル」という言葉ですが、最近よく耳にするようになりましたね。
直訳すると「持続可能な」という意味で、地球の環境を壊さず、資源を使いすぎず、未来の世代も豊かな生活をし続けていける社会を目指す、そのような考え方のことです。
「革がサステナブル」と聞くと、少し意外に感じる方も多いかもしれません。
特に近年は、環境意識の高まりから”動物由来の素材”そのものに対して懐疑的な意見が見られることがよくあります。
一方、JLIA(日本皮革産業連合会)の発信によれば、革はもともと「副産物」を活かす素材であり、むしろ資源の循環に貢献している面もあるそうです。
つまり、本来なら廃棄されてしまう「食肉の副産物」である原皮を、丁寧な加工と手入れによって長く使えるアイテムへと昇華させる。
それこそが、革製品に込められた本質的な価値だという考え方です。
確かに、10年20年と履き続けられるオールデンの革靴や、丁寧なケアによって味わいを深めるコードバンのような素材は、「消費」よりも「継続・循環」の価値観を体現しているかもしれませんね。

靴磨きの文化と“革を使い続ける”という考え方
SHOESHINE GRAND PRIXの理念は、「靴磨き文化の発信と発展」です。
今回の2025年大会でも、ただ磨きの技術を競い合うだけでなく、革靴やシューケアに関するさまざまな展示や体験コンテンツも展開されていました。
それらに共通していたのが、「革を美しく、長く使い続ける」ことの価値を伝えるという点だと感じました。
ちなみに、人類と革との関係は非常に長く、狩猟時代から人類は動物の肉を頂くと同時に、皮や骨に至るまで余すことなく活用していたといわれています。
現代は畜産が主となりましたが「副産物を無駄にしない」という考え方は変わっておらず、革を活用するということは、伝統的かつ近年のサステナブルにも寄与する行為といえるでしょう。
会場ではこうした情報がコンパクトにまとめられた広報資料として配布されていましたが、JLIAが展開する特設サイト「Tanners’ Leather Association」では、革の魅力やサステナビリティに関する内容がさらに分かりやすく紹介されています。
興味のある方は、ぜひそちらもご覧になってみてください。
「エシカルだから選ぶ」ではなく、「良いものを長く使う」
最後に私個人としては、「サステナブルだから革を選ぶ」という訳ではなくても、革製品を大切にケアして長く使うことは、結果的に持続可能な社会を支える一助になるのではないかと考えます。
以前に当ブログでは『パタゴニア』の企業理念や環境への取り組みについて紹介しましたが、それにも通じる考え方かもしれません。
つまり、「長く使える・直せる・育てられるものを選ぶ」という視点は、これからの消費において、ごく自然な価値観として定着していくのではないでしょうか。
そうした価値観の中で、磨きながら育てる革靴や、修理して履き続けられるオールデンは、これからも変わらず魅力的な存在であり続けることでしょう。
まとめ
今回は、SHOESHINE GRAND PRIXの会場で見かけた「革とサステナビリティ」の話題について少しだけご紹介させて頂きました。
持続可能、と聞くと身構えてしまいそうですが、「良いものを長く使うことが、自然と地球にも優しい」という感覚は、革靴好きにとってむしろ馴染み深いものかもしれませんね。
大会の結果発表と合わせて、革製品と環境についても少しだけ思いを巡らせて頂けると嬉しいです。
最後までお読み頂きありがとうございました。